はじめに:就労の有無に関係なく預けられる「こども誰でも通園」とは

こども家庭庁は2025年10月10日、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年度から全ての自治体で導入するのに当たり、利用時間の上限を「月10時間」とする方針を有識者会議で示した。
「こども誰でも通園制度」は保護者の就労の有無にかかわらず、0歳6か月から満3歳未満の未就園児を一時的に保育施設へ預けられる仕組みです。
10時間以上を求める声も出ているが、保育士が各地で不足している状況に配慮した。
保育士不足などで対応が難しい場合の経過措置として26~27年度の2年間は、月3~10時間未満の範囲内で自治体が上限を決められる。
制度の対象は保育園などに通っていない生後6カ月~3歳未満。
2024年度から118自治体で試験的に始まり、2025年度は250以上の自治体が先行導入する見込み。2026年度から全国展開する。
保護者が支払う利用料や、施設側に対する国や自治体の補助額は、年末の予算編成で検討する。
これまで「保育園=働く親だけが利用できる」という構図が強かった中で、育休中の親や専業家庭でも保育体験ができる点が注目されています。
発表によると、この制度は2025年度に地域子ども・子育て支援事業の一部として制度化され、2026年度には全国展開される見通しです。
一方で、保護者側からは「足りない」「信頼関係を築くのが難しい」として制度の試行段階における「月10時間」という利用上限が議論を呼んでいます。
今回は、この「月10時間」という枠が実際にどのような意味を持ち、子育て世帯にどのような影響を与えるのかを整理していきます。
引用元:
内閣府 子ども・子育て本部
こども誰でも通園「月10時間」 利用上限、26年度に全国展開
月10時間の利用上限とは?現行の試行事業を解説
「こども誰でも通園制度」は、2023年度から全国の自治体で試行事業が始まりました。
各自治体では「月10時間までの利用」を基本としています。
たとえば、さいたま市や京都市、横浜市などでは「月10時間以内」「繰越不可」「1日あたり2時間まで」などの条件が設けられています。
つまり、1週間あたりに換算すると約2.5時間しか利用できない計算です。
また、初回面談や登録手続きも利用時間に含まれる場合があり、実際に子どもが保育室で過ごせる時間はさらに短くなるケースもあります。
これにより、「本格的な保育体験というより、短時間の交流・慣らし保育に近い」という印象を受ける保護者も少なくありません。
制度が生まれた背景:多様な子育てニーズに対応するため
では、なぜこのような制度が作られたのでしょうか。
背景には、近年の子育て環境の多様化と、孤立する家庭の増加があります。
内閣府によると、この制度の目的は以下の3点です。
- 保護者の就労有無に関係なく利用できる環境整備
- 子どもの集団生活・社会性発達の支援
- 育児不安・孤立の防止や相談機会の確保
特に、核家族化が進む現代では、家庭内で子どもと1対1で過ごす時間が長く、親の精神的負担も大きいのが現実です。
短時間でも預けられる制度は、保護者にとって「自分の時間を持つ」「相談できる相手を得る」貴重なきっかけとなりえます。
また、就労していない保護者でも、保育体験を通じて子どもの成長を知り、次年度以降の入園準備に役立てられるという意義もあります。
月10時間では短すぎる?利用者の声と現場の課題
一方で、現場や保護者からは「月10時間では短すぎる」という声が多く上がっています。
慣らし保育には足りない
保育関係者からは、「子どもが環境に慣れる前に時間が終わってしまう」という指摘があります。
慣らし保育には一定の継続性が必要で、週に1回2時間程度では、毎回が“初回”のようになってしまうケースも。
子どものリズムが崩れやすい
月10時間という短期利用は、家庭と保育施設の生活リズムが合いにくく、子どもの安心感を育みにくいという課題もあります。
親の預けやすさにもばらつき
自治体によっては対応施設が少なく、予約が取りにくいケースも。
特に人気の保育園や認定こども園では枠が限られており、結果的に「使いたくても使えない制度」になる懸念もあります。
「ないよりはマシ」という現実
多くの保護者が感じているのは、「10時間では足りないけれど、ないよりは助かる」という感覚。
育児中にちょっとした時間を確保できることは確かに有難いものの、実際の生活支援としては十分とは言い難いというのが正直なところです。
政府の狙いと今後の展開
政府は2026年度からの全国展開を目指しています。
ただし、上限時間や運営方法は自治体裁量に委ねられる見通しです。
つまり、将来的には地域ごとに「より柔軟な運用」が可能になる可能性もあります。
内閣府の資料(2024年子ども・子育て会議資料)では、
「地域の実情に応じて時間数を柔軟に設定」「利用枠拡充の検討」も今後の課題として挙げられています。
つまり、現在の“月10時間”はあくまでスタートラインに過ぎず、制度を段階的に育てていく方針です。
今後の改善に期待されるポイント
| 課題 | 改善の方向性 |
|---|---|
| 利用時間が短い | 月10時間から20〜30時間への拡大、または自治体裁量で上限緩和 |
| 予約・申請の煩雑さ | オンライン予約・デジタル申請の導入 |
| 施設数の不足 | 対応施設の拡充、私立園や企業主導型保育の活用 |
| 利用料の統一性 | 所得に応じた減免制度の明確化 |
| 情報のわかりにくさ | 自治体ごとの広報強化、わかりやすい比較サイトの整備 |
こうした改善が進めば、「一時預かり制度」から「地域ぐるみの育児支援ネットワーク」へと発展する可能性があります。
おわりに:小さな一歩だが、子育て家庭に寄り添う制度に
「こども誰でも通園」は、保育を必要としない家庭にも“社会とのつながり”を提供する新しい制度です。
月10時間という上限には課題が残りますが、少しでも子どもを預けられる時間があることで、親の心に余裕が生まれるのも事実です。
ただし、これを「十分な支援」とするのではなく、あくまでスタート地点として捉えることが大切です。
制度が定着・改善されることで、より多くの家庭が気軽に保育の力を借りられる社会へと近づいていくでしょう。
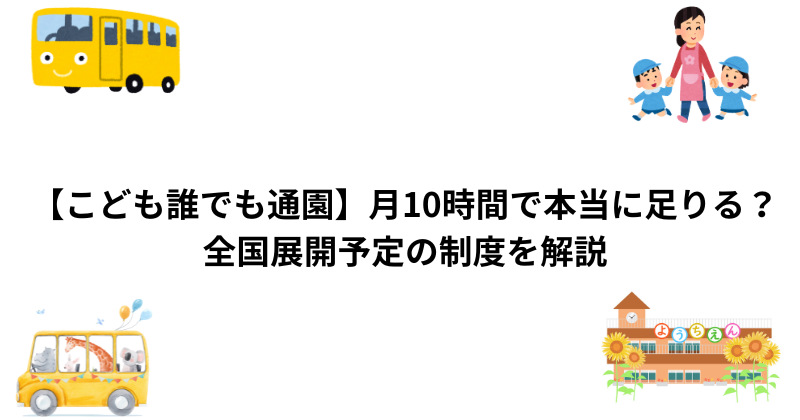

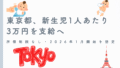
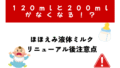



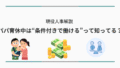

コメント