「ボーナス、いつ出るかな?」なんて、従業員の方々が楽しみにしている賞与。
経営者や人事担当者の方にとっては、その設計や運用に頭を悩ませることも多いのではないでしょうか?

他社ってどんな考え方で賞与を出しているんだろう?

うちの会社の賞与制度って、これで本当にいいのかな?
もしあなたがそんな疑問や課題を抱えているなら、この記事がきっとお役に立ちます。
今回は、賞与が持つ2つの大切な性質から、具体的な支給パターン、そして賞与の「元手(原資)」の決め方まで、分かりやすく解説していきますね。
賞与が持つ2つの大切な意義
まずは、賞与がそもそもどんな意味合いを持っているのか、一緒に見ていきましょう。
賞与には、大きく分けて2つの性質があります。
① 賃金の後払い(生活保障)としての賞与
これは、日々の給与では賄いきれない、従業員の生活を補完する意味合いを持つものです。
例えば、ボーナス払いで家電や携帯を買い替えたり、子供の誕生日プレゼント代に当てるなどです!
安定した生活を支える上で、賞与が果たす役割は大きいんです。
賞与をなくすという話が出た際に、社員からそれでは家の住宅ローンはどうするのか?ボーナス払い分はどうするのか?と言った話が出るのです。
② 業績貢献に対する報酬としての賞与
もう一つは、従業員の日々の頑張りや会社の業績への貢献を評価し、報いるという意味合いです。
会社の業績が良ければ賞与が増え、個人の成果が認められれば、それが賞与額に反映される。
こうすることで、従業員の皆さんの「よし、もっと頑張ろう!」というモチベーションアップにもつながるわけですね。
業績に応じて支給額が変動する性質を持つ賞与は、従業員一人ひとりの業績意識を高める上で、とても有効なツールと言えます。
実は、法律で賞与の支給が義務付けられているわけではありません。
しかし、厚生労働省の「令和5年賃上げ等の実態に関する調査」によると、なんと86%もの企業が賞与を支給しているんです。
これは、多くの企業が賞与の持つこれらの意義を理解し、積極的に活用している証拠と言えるでしょう。
具体的な賞与の支給パターンをチェック!
次に、実際に賞与をどうやって計算して支給しているのか、そのパターンを見ていきましょう。
主な方法として、「月給連動方式」「算定基礎額方式」「ポイント方式」の3つがあります。
① 月給連動方式
これは、皆さんが一番イメージしやすいかもしれませんね。
月給連動方式=月給×支給月数×人事評価係数
この「月給」には、基本給に加えて役職手当などを含めることが多いです。
例えば、「基本給+役職手当」を月給として、そこに「2ヶ月分」や「3ヶ月分」といった支給月数を掛け合わせ、さらに人事評価の結果に応じた「人事評価係数」を掛けて計算します。
シンプルで分かりやすいのが特徴です。
特に求人票にもこのような記載をしている企業が多いですし、求職者がかなり見る部分ですよね!→余談ですが、求職者からしたら質問しにくいですが、絶対確認している部分です。
② 算定基礎額方式
月給連動方式と似ていますが、こちらは「月給」ではなく、等級や役職ごとにあらかじめ決めた「算定基礎額」を使うのが特徴です。
算定基礎額方式=算定基礎額×支給月数×人事評価係数
例えば、「課長職は算定基礎額30万円」のように設定します。
これにより、同じ役職であれば、個人の月給額の違いに関わらず、賞与の基礎となる金額を一定に保つことができます。
大手企業のような従業員数が多いかつ年功序列型の賃金体系を取っている企業がこのような仕組みを取っている傾向です。
③ ポイント方式
これは、少し独特な計算方法ですが、多くの企業で導入が進んでいる方式です。
ポイント方式=ポイント単価×人事評価ポイント
この方式では、まず従業員一人ひとりの人事評価に応じて「人事評価ポイント」を付与します。
そして、
会社の「賞与原資」を「従業員全員の評価ポイントの合計」で割ることで、「ポイント単価」を算出します。
ポイント単価 = 賞与原資 ÷ 従業員の評価ポイントの合計
このポイント方式の大きなメリットは、
予定している賞与原資を上回ることがない
という点です。
月給連動方式や算定基礎額方式の場合、計算結果として想定以上の原資が必要になってしまうこともあり得ます。
その場合は、「支給月数」を抑えることで調整する、といった対応が必要になりますが、ポイント方式ならその心配が少ないと言えるでしょう。
人事評価係数とは?
「人事評価係数」や「評価ランクに応じた支給率」と出てきましたが、これは人事評価の結果に応じて、賞与の支給額を調整するための係数のことです。
例えば、最高評価なら1.2倍、標準評価なら1.0倍、といった形で設定されます。
また、賞与の支給と人事評価のタイミングですが、もし年2回それぞれ行われる会社であれば、一般的には以下のように反映されます。
- 上期評価結果(3月決算の会社なら10月頃に評価が固まる場合が多いですね)は、冬季賞与に反映
- 下期評価結果(翌年3月頃に評価が固まる場合が多いですね)は、翌年度の夏季賞与に反映
このように、人事評価と賞与支給のタイミングを連動させることで、従業員の皆さんのモチベーションを継続的に高める効果が期待できます。
賞与の「元手(原資)」はどうやって決める?
さて、賞与の計算方法が分かったところで、その元となる「賞与原資」をどうやって決めているのでしょうか?
ここには、大きく分けて
「総合決定方式」と「業績連動方式」の2つの方法があります。
① 総合決定方式
これは、会社の業績や個人の評価、市場の動向、そして過去の賞与支給実績など、さまざまな要素を総合的に考慮して賞与原資を決定する方法です。
長年、多くの日本企業で主流とされてきた方式で、
安定的な支給が見込める反面、
業績の変動が賞与にすぐに反映されにくい
という側面もあります。
② 業績連動方式
近年、特に導入が進んでいるのが、この「業績連動方式」です。これは、会社の特定の業績指標に連動して賞与原資を決定する方法です。
経団連の「2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を見ると、なんと55.2%もの企業で業績連動方式が導入されていることが分かります。
これは、企業の業績と従業員の報酬をより密接に結びつけようとする動きが活発になっていることを示しています。
では、どんな業績指標が基準として使われているのでしょうか?調査によると、
- 営業利益:60.2%
- 経常利益:34.3%
が主流となっています。
営業利益は本業での稼ぐ力を、経常利益は本業以外の収益や費用も含めた企業全体の利益を示す指標ですね。
これらの指標を基準とすることで、会社の業績が良ければ賞与が増え、従業員がより会社の目標達成に意識を向ける効果が期待できます。
まとめ
今回は、賞与の意義から具体的な支給方法、そして原資の決定方法まで、幅広くご紹介しました。
賞与は単なるお給料の一部ではなく、「生活保障」と「業績貢献への報酬」という2つの大切な役割を持っています。
そして、その支給方法や原資の決定方法は、企業の文化や戦略によって様々です。外資系の基本的な給与体系である、年棒型を導入してボーナスを廃止している企業もあったり、ボーナスではなく決算賞与のみで会社の売上・利益の結果のみで判断する企業も増えてきている状況です。
他社の事例を知ることで、

うちの会社では、どんな賞与制度が従業員のモチベーションを高め、会社の成長につながるだろう?と考えるきっかけになったのではないでしょうか。
この記事が、あなたの会社の賞与制度をより良くするためのヒントになれば嬉しいです。
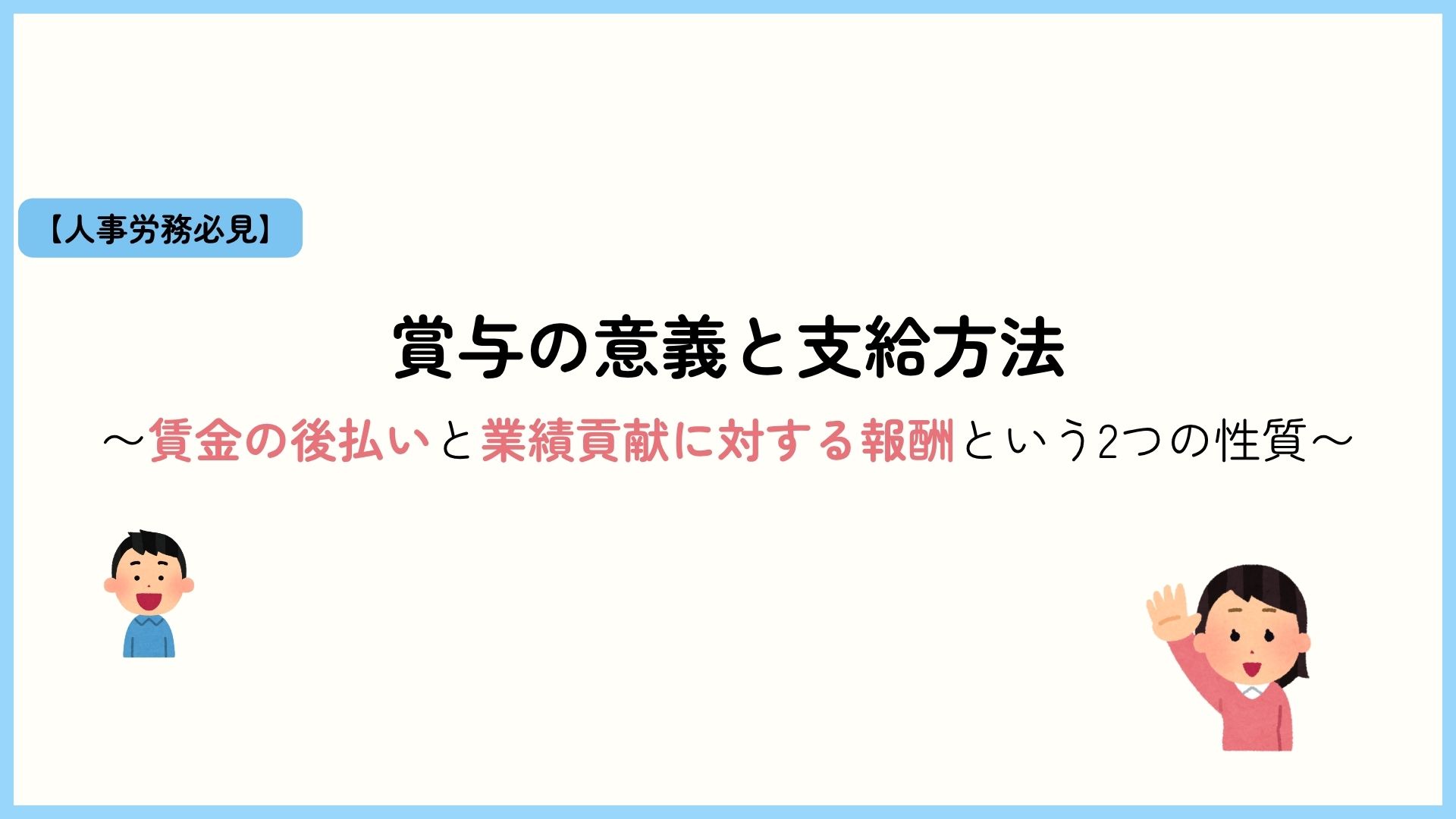







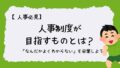
コメント