「子どものため」と思ってやっていることが、実は子どもの心に深いストレスを与えているかもしれません。私たちは日々、無意識のうちに子供を傷つけるような言動を取ってしまっていないでしょうか。
この記事では、親がやりがちな「10のNG言動」を解説します。単に「ダメ」と指摘するだけでなく、なぜそれが問題なのか、どのような科学的研究がそれを裏付けているのか、そして明日からすぐに実践できる具体的な対策を詳しくお伝えします。
お子さんとの関係をより良くし、互いが笑顔でいられる家庭を築くためのヒントが、きっと見つかるはずです。
ため息をつきながら関わる
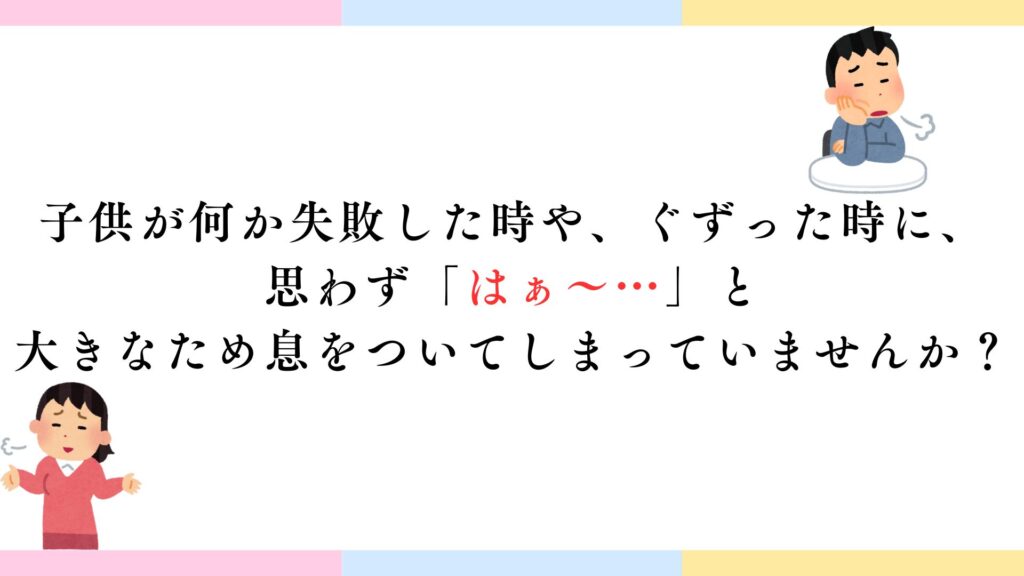
なぜダメなのか|子どもに「自分の存在が迷惑」だと感じさせてしまう
言葉にせずとも、ため息は「うんざりしている」「面倒くさい」といったネガティブな感情を伝えてしまいます。子どもは親の非言語的なサインに非常に敏感です。親がため息をつくたびに、子どもは「自分の存在が親を疲れさせている」「自分は親に嫌われているのかもしれない」と感じ、強い罪悪感や自己肯定感の低下を招きます。これは、親から直接否定されたわけではなくても、無言の圧力として子供の心に深く刻まれるのです。
研究結果|親のネガティブな感情は子どもに伝播し、情緒不安定を引き起こす
心理学の研究では、親の感情状態が子どもの情緒安定に直接的な影響を与えることが明らかになっています。親がストレスや不安を抱えていると、そのネガティブな感情は子どもに伝播し、子ども自身の癇窭や情緒不安定さを引き起こしやすくなるという報告があります。ため息は、まさに親のストレスの表れであり、それが子供の心に間接的に悪影響を及ぼすのです。
対策
- 深呼吸で感情をリセットする:
ため息が出そうになったら、一度立ち止まり、深く息を吸い込んで吐くように意識します。これは親自身のストレスを軽減するセルフケアにもなります。 - 言葉で気持ちを伝える:
「ちょっと疲れたから、少し休ませてね」のように、ため息の代わりに言葉で状況を説明します。これにより、子どもは親の状況を理解しやすくなり、「自分のせいではない」と安心できます。 - 一人の時間を作る:
ストレスが溜まっていると感じたら、短時間でも一人になる時間を作り、心に余裕を持たせるようにしましょう。
他の子どもと比較する
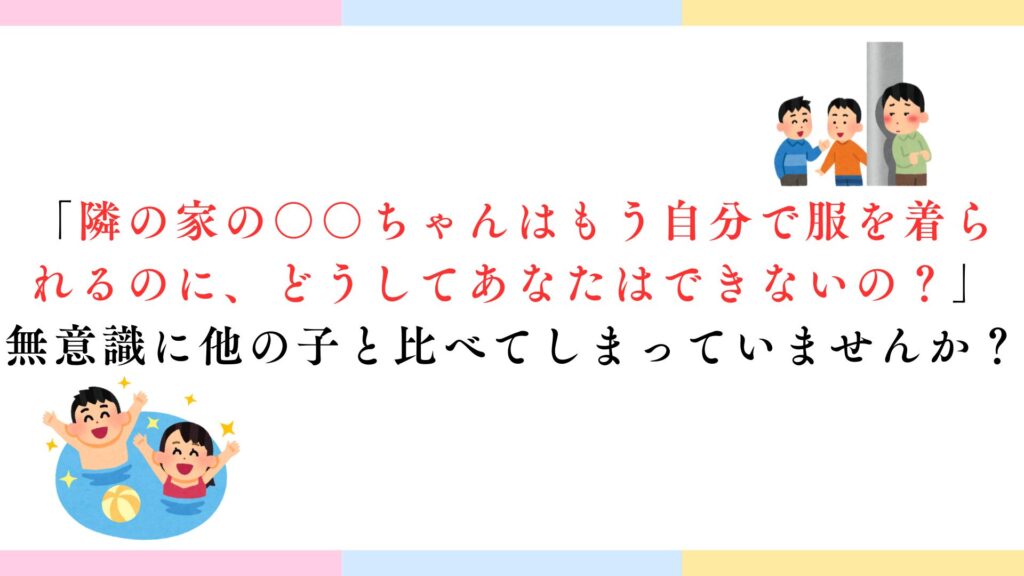
なぜダメなのか|子どもの自尊心を傷つけ、劣等感や嫉妬を植え付ける
「〇〇ちゃんはできるのに、どうしてあなたはできないの?」という比較の言葉は、子どもにとって「あなたはありのままで価値がない」というメッセージに他なりません。子どもは、自分と他者を比べて劣等感を感じるだけでなく、比較対象となった相手に対しても嫉妬や嫌悪の感情を抱くことがあります。これにより、健全な人間関係を築く能力が阻害される可能性もあります。
研究結果|自己肯定感の低下に繋がり、健全な人間関係を妨げる可能性がある
同志社大学の研究論文「子どもの自己肯定感に及ぼす影響要因に関する実証研究」(古荘、2009年)など、複数の研究で、日本の若者は欧米やアジアの他国と比べて自己肯定感が低い傾向にあることが示されています。親からの頻繁な比較は、こうした自己肯定感の低下に拍車をかける要因の一つと考えられています。
※上記の研究では、自己肯定感に影響を与える要因には「性別」,「経済的要因」(「低収入」)と「関係的要因」(【親への信頼】【親との親密さ】【親戚との関係】【親の学業干渉】【学校生活享受感】【学業満足度】【友人の多さ】)が挙げられています。
参考文献:子どもの自己肯定感に及ぼす影響要因に関する実証研究
対策
- 過去の自分と比較する:
「前はこれができなかったけど、今はできるようになったね!」のように、お子さん自身の成長に焦点を当てて褒めます。 - 長所や個性を認める:
「絵を描くのが上手だね」「優しい心を持っているね」など、お子さん独自の才能や性格を具体的に褒めることで、自己肯定感を育みます。 - 親自身の比較癖を見直す:
親自身もSNSなどで他者の子育てと比べていないか、意識的に見直すことが重要です。
子どもの話を最後まで聞かない(話を途中で遮る)
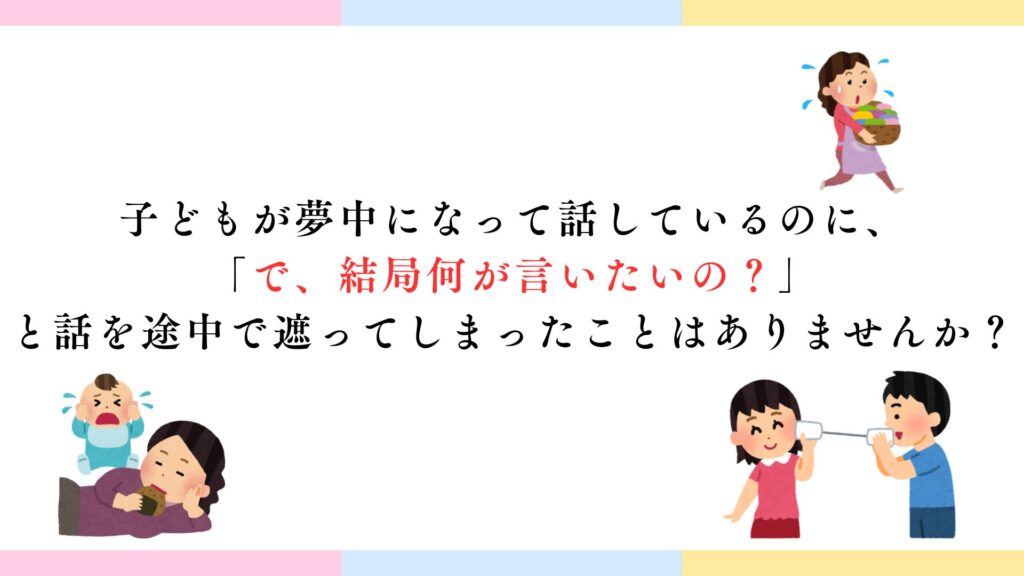
なぜダメなのか|「自分の話には価値がない」と孤立感を抱かせる
話を途中で遮る行為は、「あなたの話には価値がない」「あなたの感情は重要ではない」というメッセージを子どもに伝えます。これにより、子どもは「どうせ話しても無駄だ」とコミュニケーションを諦めるようになり、親子の信頼関係に亀裂が入ります。また、自分の感情をうまく表現できなくなることで、将来的に感情のコントロールが苦手になる可能性もあります。
研究結果|自己表現の意欲を失い、言語能力の発達を阻害する
心理学では、相手の話を最後まで聞き、共感を示す「傾聴」が重要だとされています。教育心理学の分野では、親が子どもの話を熱心に聞くことで、子どもの言語能力や感情の発達が促進されることが証明されています。逆に、話を遮られる経験が続くと、子どもは自己表現への意欲を失い、言葉の発達が遅れるリスクも指摘されています。
対策
- 「最後まで聞く」を意識する:
まずは最後まで聞き、質問や返答はその後にします。 - 相槌やアイコンタクトを増やす:
「うんうん」「それで?」といった相槌や、目を合わせることで、「ちゃんと聞いているよ」という姿勢を伝えます。 - 「聞く時間」を設ける:
忙しい時でも、「5分だけママに話していい?」と時間を区切ることで、子どもの話を聞く機会を意識的に作ります。
親の気分で態度が変わる
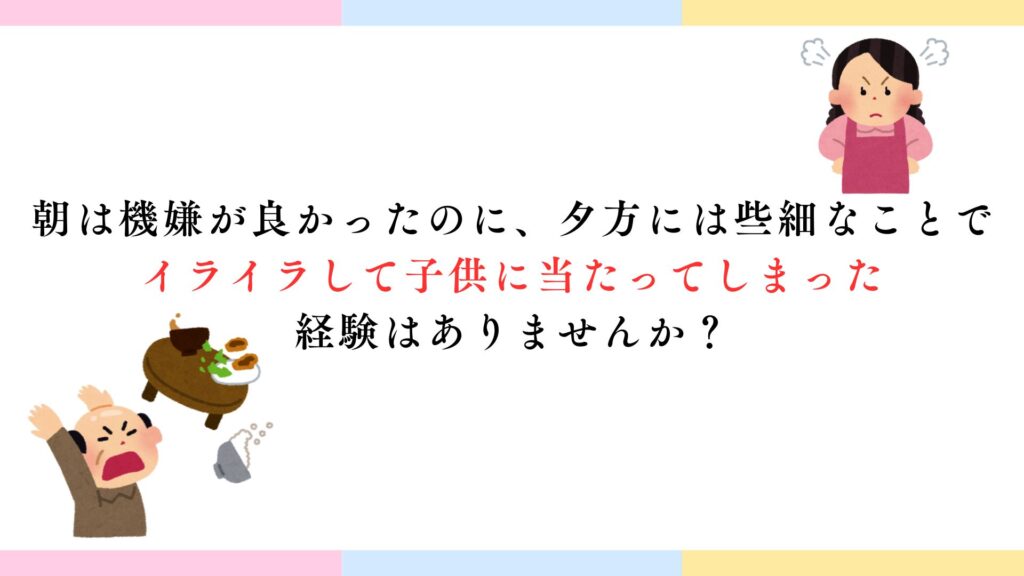
なぜダメなのか|子どもが常に不安に苛まれ、親の顔色をうかがうようになる
親の感情が不安定で、日によって態度がコロコロ変わると、子どもは「親はいつ怒るかわからない」という不安に常に苛まれます。これは「安全基地」であるべき家庭が、いつ地雷が爆発するかわからない場所になってしまうことを意味します。子どもは親の顔色をうかがうようになり、委縮して自分の意見を言えなくなったり、情緒が不安定になったりします。
研究結果|「愛着理論」において、情緒不安定な愛着形成の原因となる
イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィが提唱した「愛着理論(Attachment Theory)」では、子どもの心の安定には「安全基地」としての親の存在が不可欠だとされています。親が安定した態度で一貫した愛情を注ぐことで、子どもは安心して世界を探求できるようになります。一方で、親の態度が不安定だと、子どもは「不安型愛着」を形成しやすくなり、将来的に対人関係で不安定さや依存傾向を示すリスクが高まります。この理論は、黒田・高橋ら日本の研究者によっても紹介され、親子関係のあり方に関する多くの研究に影響を与えています。
対策
- 自分の感情を客観視する:
「今、自分はイライラしているな」と自覚することが第一歩です。 - 感情の切り替えを意識する:
イライラしている時は、「少し落ち着こう」と自分に言い聞かせたり、深呼吸をして気持ちを切り替えたりします。 - 感情の起伏を子供のせいにしない:
疲労や仕事のストレスなど、親の個人的な感情の揺れを子供にぶつけないように注意します。
否定的な言葉や人格否定
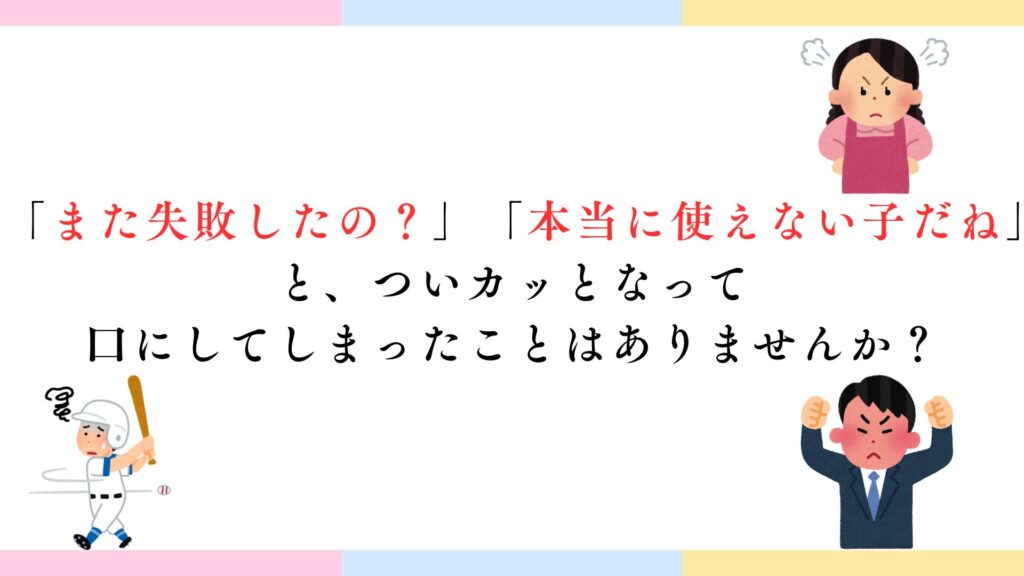
なぜダメなのか|子どもの自己肯定感を著しく低下させ、「自分はダメな人間」だと思い込ませる
「なんでいつもそうなの?」「本当に使えない子だね」といった言葉は、子どもの人格そのものを否定する最悪の言動です。このような言葉を浴びせられると、子どもは「自分はダメな人間だ」と思い込み、自己肯定感が急激に下がります。この状態が続くと、うつ病や不安障害などの精神疾患のリスクを高めるだけでなく、将来的に人間関係を築くことに強い恐怖を抱くようになります。
研究結果|言葉の暴力は脳に物理的な変化を引き起こす
福井大学の友田明美教授らの脳科学研究は、言葉による精神的な暴力が、子どもの脳に物理的な変化を引き起こすことを明らかにしました。彼らの研究によると、親からの暴言を日常的に浴びせられた子どもは、聴覚野や言語理解を司る脳の部位の容積が縮小することがわかっています。友田教授は著書『子どもの脳を傷つける親たち』の中で、「言葉の暴力は、身体の表面には傷をつけないが、心や脳に傷をつける」と警鐘を鳴らしています。
対策
- I(アイ)メッセージを使う:
「あなたは〜」と主語を子どもにするのではなく、「ママは〜と感じたよ」と主語を自分にします。例:「また部屋が散らかって!」→「部屋が散らかっていると、ママは片付けるのが大変だと感じるよ」 - 行動と人格を分けて叱る:
「片付けないのはダメな子」ではなく、「片付けをしないのは良くないこと」と、行動に焦点を当てて伝えます。 - ポジティブな言葉を意識的に使う:
「ありがとう」「助かったよ」「すごいね」など、日頃から褒める言葉や感謝の言葉を増やすよう心がけます。
過干渉・支配
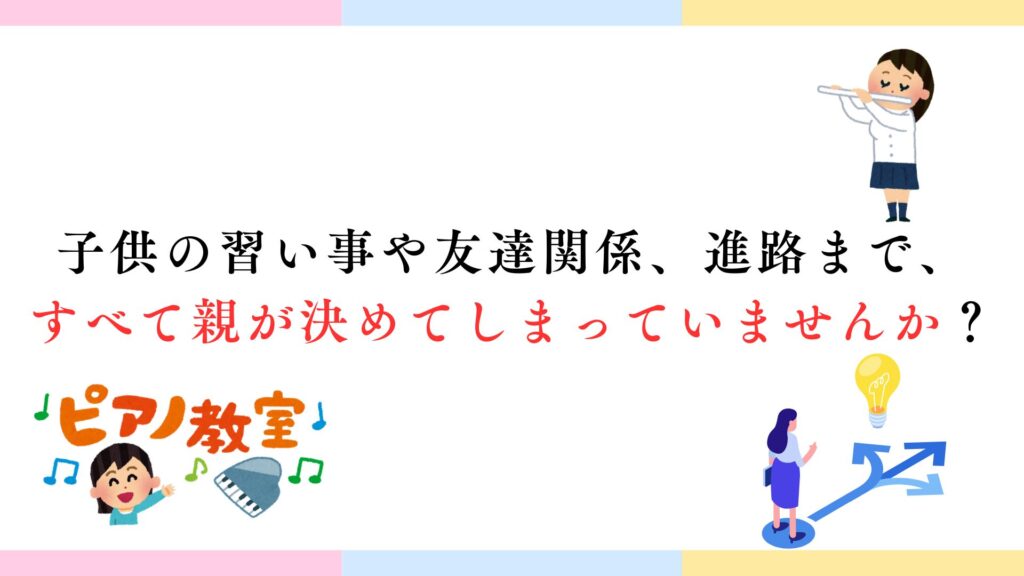
なぜダメなのか|子どもの自立心を奪い、自分で考える力を育てられない
子どもの自主性を尊重せず、親が何から何まで決めてしまう行為は、子供の自立心を奪います。習い事や進路、友達関係に至るまで親が口出しすると、子どもは自分で考え、選択し、行動する機会を失います。その結果、自分で物事を決められない「指示待ち人間」になったり、逆に親への強い反発心から、自暴自棄な行動に出てしまうこともあります。
研究結果|自己効力感の低下に繋がり、主体的な行動を妨げる
心理学において、自分の力で目標を達成できると信じることができる感覚を「自己効力感」と呼びます。広島大学などの研究でも、親からの過度な干渉や過保護な養育態度が、子どもの自己効力感を低下させる可能性が指摘されています。自己効力感が低いと、子どもは将来的に主体的に物事を考えたり、挑戦したりする意欲を失いやすくなります。
対策
- 「見守る」姿勢を意識する:
子どもが自分でできることは、口を出さずに見守ります。 - 「選択肢」を与える:
「〜しなさい」ではなく、「AとB、どっちがいい?」と選択肢を与え、自分で決めさせる機会を作ります。 - 小さな失敗を許容する:
失敗から学ぶことも重要です。「失敗しても大丈夫」というメッセージを伝えます。
完璧主義の押し付け
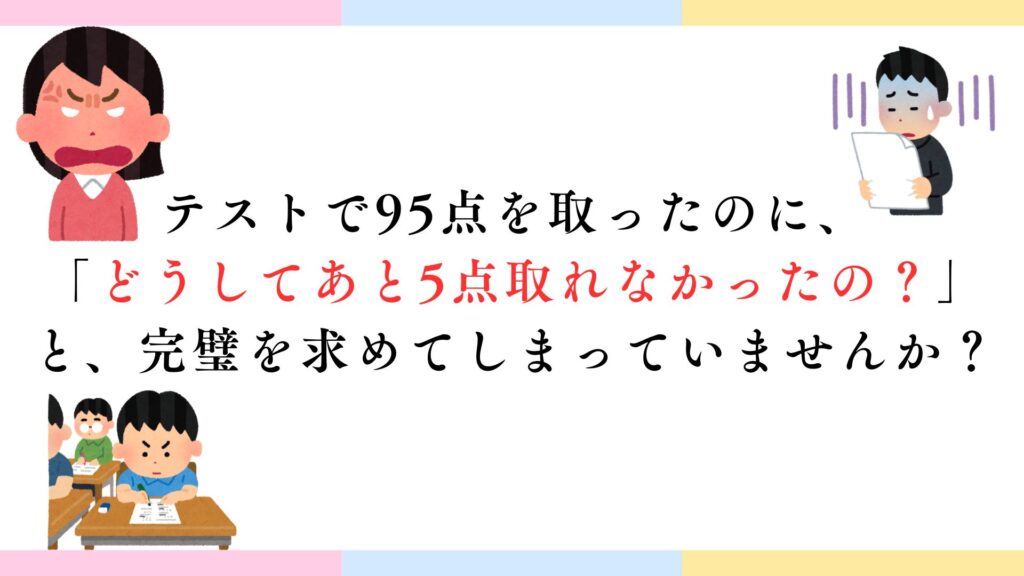
なぜダメなのか|失敗を過度に恐れさせ、新しいことに挑戦する意欲を削ぐ
完璧を求める親の言動は、子どもに「失敗は許されない」という強迫観念を植え付けます。子どもは常に100点満点を目指さなければならないと感じ、少しのミスでも自分を激しく責めるようになります。これは、新しいことに挑戦する意欲を削ぎ、不安や恐怖から行動をためらうようになります。
研究結果|子どもの完璧主義や精神疾患のリスクを高める
アルガルヴェ大学の研究など、海外の研究では親の完璧主義的な養育態度が、子どもの完璧主義的な傾向を強めることが示唆されています。また、筑波大学などの研究でも、親の完璧主義と子どもの完璧主義には正の相関があることが報告されており、特に同性の親と子どもの間でその傾向が強いというデータもあります。このことは、子どもが親の言動をモデルとして学習している可能性を示しています。
対策
- 「頑張り」の過程を評価する:
結果だけでなく、「一生懸命に頑張ったね」と過程を褒めます。 - 「失敗」をポジティブに捉える:
「失敗は成功のもと」という考え方を共有し、「次はどうすればうまくいくかな?」と一緒に考えます。 - 親自身も「完璧」を手放す:
親が自分の完璧主義を自覚し、自分自身に対しても「完璧じゃなくても大丈夫」と許すことが大切です。
夫婦喧嘩や家庭内の緊張感
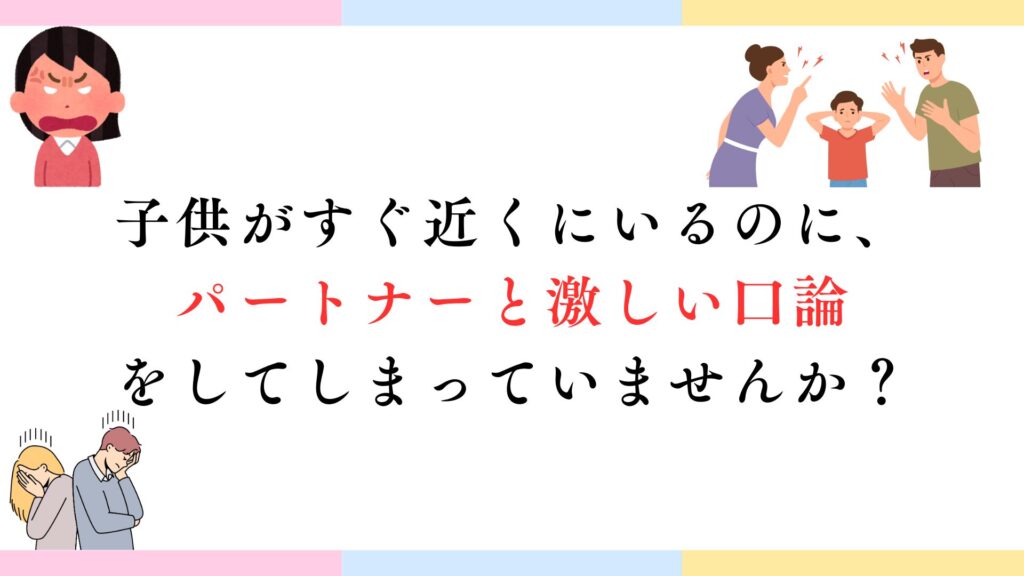
なぜダメなのか|子どもに計り知れない恐怖とストレスを与える
夫婦喧嘩は、子どもに計り知れない恐怖とストレスを与えます。子どもは親の口論や怒鳴り声を聞くたびに、「自分のせいかもしれない」「家庭が壊れてしまうかもしれない」という不安に苛まれます。家庭が安全な場所ではなくなることで、子どもは情緒不安定になったり、集中力が低下したり、頭痛や腹痛といった身体的な症状を訴えることもあります。
研究結果|脳の発達に悪影響を及ぼし、感情のコントロールを困難にする
福井大学の友田明美教授らの脳科学研究では、夫婦喧嘩を目撃することが、子どもの脳に物理的な変化を引き起こすという事実が明らかになっています。激しい口論や暴力は、ストレスホルモンであるコルチゾールを過剰に分泌させ、脳の海馬や前頭前野といった重要な部位の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。ある研究では、夫婦喧嘩を長期間見続けた子どもは、他人の感情を読む能力に欠けたり、自分の感情をコントロールする能力が低くなる傾向があることが示されています。
対策
- 子供のいない場所で話し合う:
意見の衝突は避けられないこともありますが、子供の目の前での激しい口論は避けます。 - 話し合いの姿勢を見せる:
怒鳴り合うのではなく、落ち着いて話し合って解決しようとする姿勢を子供に見せることは、子供に安心感を与えます。 - 「仲直り」の姿を見せる:
喧嘩をしてしまった後でも、きちんと仲直りする姿を見せることで、「喧嘩しても最後は大丈夫」という安心感を植え付けることができます。
「早くして」「まだ」を繰り返し連呼する
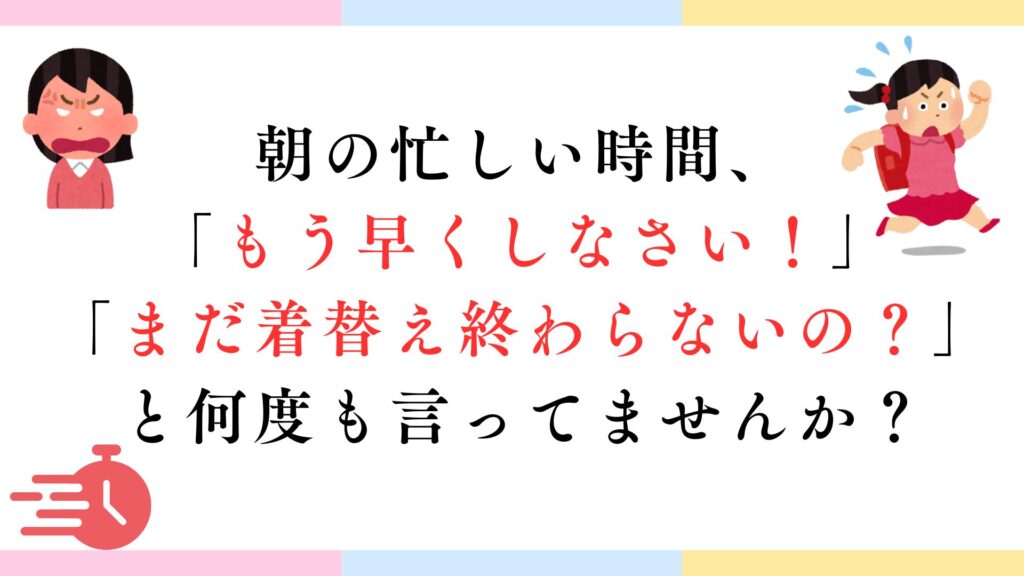
なぜダメなのか|子どもに常に焦りやプレッシャーを与え、集中力を奪う
「早くしなさい!」「もう、まだやってるの?」という言葉は、子どもに常に「急かされている」という感覚を与えます。まだ大人ではない子どもは自分のペースがあります。大人と比べて早く行動しにくい子どもは自分のペースで物事を進めることができなくなり、常に焦りやプレッシャーを感じます。その結果、集中力が低下したり、行動がさらに遅くなったりする悪循環に陥ることがあります。
研究結果|子どもの自己調整能力の発達を阻害する可能性がある
心理学の研究では、親からの「早く」という圧力は、子どもの自己調整能力の発達を阻害する可能性が指摘されています。子どもは、自分の内的な動機に基づいて行動する機会を失い、常に外部からの指示を待つようになります。これは、将来的に時間管理や自己管理が苦手になる原因の一つになり得ます。
対策
- 時間的な余裕を持つ:
朝の準備や出かける時間など、あらかじめ時間に余裕を持って行動する計画を立てます。 - 声かけをポジティブに変える:
「早く」ではなく、「〜までにお着替えできるかな?」「あと5分で出発だよ」のように、具体的な時間や目標を伝えます。 - 親自身の時間感覚を見直す:
自分の時間感覚がタイトすぎないか、親自身が立ち止まって見つめ直すことが大切です。
スマホを見ながら話を聞く
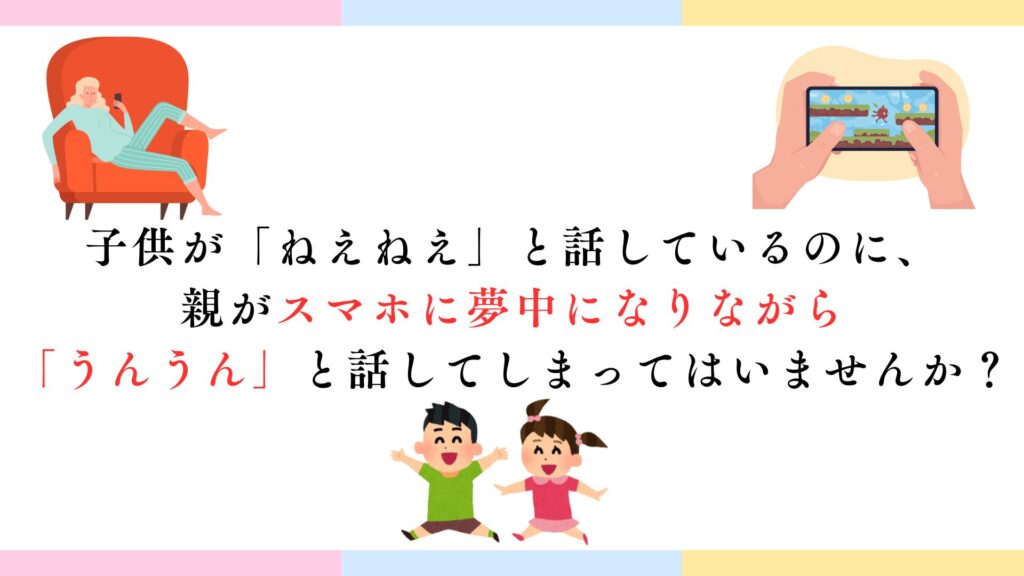
なぜダメなのか|「自分は親にとって二の次」だと感じ、孤立感を覚える
親がスマホに夢中になっている時に子どもが話しかけても、親の意識は画面に向いており、子どもは「自分は親にとって二の次だ」と感じてしまいます。この行為は、子どもとの信頼関係を築く上で非常に重要である「非言語的なサイン」をすべて遮断してしまいます。子どもは、親が真剣に話を聞いてくれていないと感じ、話す意欲を失い、孤立感を覚えるようになります。
子どもにとって「目を見て話してもらえる」ことは自分が大切にされている証拠です。また子供にとって「話を聞いてもらえること」は最高の愛情表現です。
研究結果|親子の対面コミュニケーションを阻害し、言語発達や愛着形成に悪影響を及ぼす
日本小児科医会は、2004年から「見直しましょうメディア漬けの子育て」などの提言を継続的に行い、乳幼児への長時間にわたる電子メディアの接触が心身の発達にネガティブな影響を及ぼす可能性について警鐘を鳴らしています。特に、親子の対面コミュニケーションの減少は、子どもの言語発達や愛着形成を阻害するリスクが指摘されています。
また心理学の研究でもアイコンタクトが不足すると、子どもは孤立感が強まるとされています。「自分の話は価値がない」と思わせてしまうのです。
対策
- 「スマホを置く時間」を決める:
夕食中や、子供が話しかけてきた時など、スマホを手に取らない時間を決めます。 - 「ごめんね、今集中してるから、あと5分後に話を聞かせて」と正直に伝える:
スマホを使う必要がある時は、正直にその理由を伝え、「話を聞く時間」を後で必ず設けます。 - 親子で「デジタルデトックス」デーを設ける:
週末など、家族全員がスマホやゲームから離れて過ごす時間を作ることも有効です。
まとめ

今回は、親が子どもに無意識に与えているかもしれない10のストレス源について掘り下げてきました。
子育ては、決して完璧である必要はありません。大切なのは、自分の言動が子どもにどのような影響を与えているかを知り、意識的に改善しようとすることです。
もし、今回の記事で心当たりのある項目があっても、自分を責める必要はありません。親だって人間です。疲れている時、余裕がない時もあります。
しかし、この10のポイントを頭の片隅に置いておくことで、ふとした瞬間に「あ、今ため息をついてしまったな」「つい他の子と比べてしまったな」と気づくことができます。その気づきこそが、子育てをより良い方向へと導く第一歩です。
この記事が、お子さんとより深く、より温かい関係を築くための一助となれば幸いです。
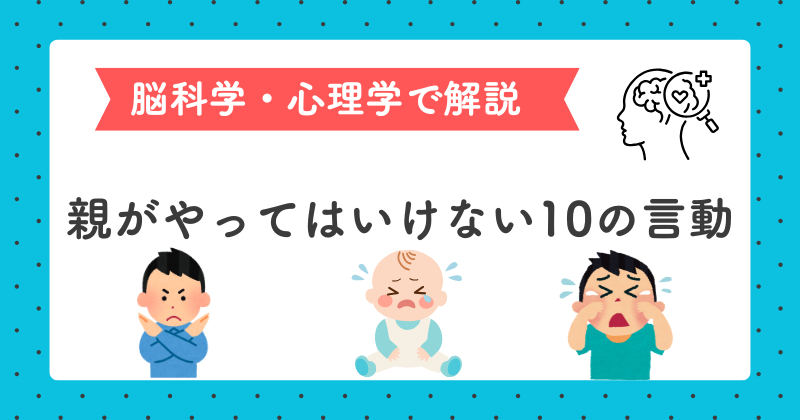
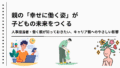
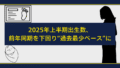
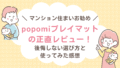

コメント