政府は少子化対策の財源として、2026年(令和8年)4月から「子ども・子育て支援金」を医療保険料に上乗せして徴収する新制度を導入します。国民1人あたりの平均拠出額は月額数百円程度(目安:約450円)とされ、児童手当の拡充や出産・育児支援、育児休業中の給付など幅広い施策に充てられる予定です。徴収の仕組みは健康保険料と同様に設定される見通しで、被用者保険に加入する会社員の場合は「労使折半」が基本とされるため、従業員本人の負担に加えて企業側の負担も増える可能性があります。
このため「企業の人件費増につながるのでは」といった経済界の懸念や、中小企業の経営負担をどう軽減するかが大きな論点となっています。また、子どもがいない世帯や独身者も一律で負担することから「実質的な独身税ではないか」との批判も根強く、社会的な公平性をめぐる議論が広がっています。政府は「全世代型社会保障」の一環として説明していますが、導入により企業の総額人件費や家計の実質負担がどの程度になるのか、今後の試算と運用設計が注目されています。
何が変わるのか(概要)
- 開始時期:
2026年(令和8年)4月から拠出(徴収)が始まる予定。 - 徴収の仕組み:
医療保険料(健康保険、国民健康保険など)に上乗せして毎月徴収する仕組み。加入者1人あたりの平均拠出額は月額450円程度が目安と説明されています(政府試算)。 - 使途(給付内容の主な例):
児童手当の抜本拡充(所得制限撤廃・高校生まで延長等)、妊婦・出産支援(出産・子育て応援交付金等)、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付など、ライフステージを通じた支援に充てられます。
企業(事業主)への影響 — なぜ企業負担が想定されるのか
制度の設計上、医療保険料に上乗せして徴収する形は 「被用者保険(会社員等)の場合、労使折半での負担」 といった想定の解説が多く出ています。つまり、従業員本人が負担する分と、事業主が負担する分を半分ずつにするケースが一般的に想定されており、企業の人件費・社会保険負担が相対的に増える可能性があります。
なぜ「企業の負担増」になるのか(ポイント)
- 労使折半の慣行:
健康保険料は多くの被用者保険で労使折半が原則。上乗せ分も同様に扱われれば、会社負担分(事業主負担)が増える。 - 給与計算・システム改修コスト:
保険料率・控除項目の変更が必要になり、給与計算システムや勤怠・給与ワークフローの改修コストが発生する見込み。 - 中小企業の影響:
従業員数が多い事業所ほど総額負担が大きくなるため、賃金や採用、福利厚生の見直しを迫られる企業も想定される。
数字で見る影響(試算例)
※政府の「平均拠出額 月額450円」を前提に、労使折半(企業が半分)で計算します。出典を踏まえた想定例です。
- 加入者1人あたりの平均拠出(目安)= 450円/月。 農林水産省
- 事業主(企業)が負担する想定(折半)= 450 ÷ 2 = 225円/月。
- 計算(桁ごと): 450 ÷ 2 = 225。
- 例:従業員100人の企業の場合、企業負担は月 225 × 100 = 22,500円。年間では 22,500 × 12 = 270,000円。
- 月計算:225 × 100 = 22500。
- 年計算:22500 × 12 = 270000。
この額はあくまで平均値(目安)の試算で、実際の負担は被保険者ごとの保険料率や所得構成、保険種類(協会けんぽ、組合健保、国保等)によって変動します。
導入に対する主な論点・批判
企業は何をすべきか(実務的な対応策)
- 給与計算・システムの早期確認:
保険料率の変更に伴う給与システムや勤怠連携の影響を事前に把握し、税理士・社労士と対応計画を立てる。 - 総額人件費の試算:
従業員数別・給与水準別の負担増シミュレーションを行い、年度予算に反映する。上の試算手法を使って簡易計算しておくと現場が動きやすい。 - 従業員向け説明の準備:
なぜ保険料が変わるのか、給付側(児童手当拡充や育児支援)でどのようなメリットが期待されるのかを整理し、社内FAQなどで丁寧に説明する。 - 福利厚生の見直し:
採用競争力維持のため、育児支援や時短勤務支援の充実(制度設計と手続き)を検討する。政府が新たに設ける給付(出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金など)と組み合わせた支援策を設計すると効果的。
見通しとまとめ(編集部コメント)
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策のための財源確保と給付拡充を同時に目指す大きな制度変更です。1人あたり月数百円という数字は一見小さいものの、労使折半の形で運用されれば事業主の総費用は無視できない規模になります。制度の受益者(子育て世帯)と負担者(広く社会)が分かれるため、政治的・社会的な議論は当面続く見込みです。政府の公式説明や自治体ごとの運用ルール・軽減措置を注視するとともに、企業は給与計算や人件費計画の早めの点検をお勧めします。
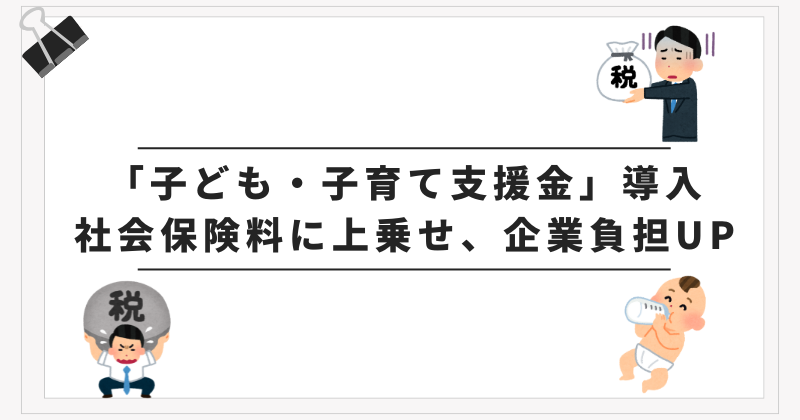

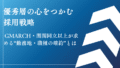
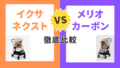
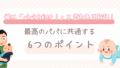


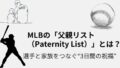
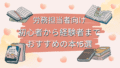
コメント