日本プロ野球機構(NPB)は2025年10月14日、選手が出産立ち会いや冠婚葬祭などの家庭事情によりチームを離れる場合、従来の登録抹消から10日間の再登録制限を待たずに復帰できる「慶弔休暇特例」を2026年シーズンから導入する方針を発表した。
日本プロ野球選手会との協議を経て正式に合意されたこの新制度は、プロ野球選手のワークライフバランス改善を目的とした、画期的な取り組みといえる。
制度の概要
この「慶弔休暇特例」は、選手が家族の出産、結婚、葬儀などやむを得ない事情でチームを離れる際、特例として短期間で再登録を可能にする制度だ。
これまでは出場選手登録を抹消された場合、最低10日間は再登録できない決まりがあったため、チームも選手も柔軟に対応できなかった。
今後は、対象となる事由を限定(出産・冠婚葬祭・近親者の重病など)したうえで、届出や証明書を提出すれば、数日で復帰できる運用が見込まれている。
これにより、選手が「家族を優先する選択」をしやすくなり、球団も戦力調整の自由度を保てるようになる。
背景と導入に至った理由
① MLBの「父親リスト」制度が刺激に
背景には、アメリカ・メジャーリーグ(MLB)の制度運用がある。
MLBではすでに「父親リスト(Paternity List)」が存在し、選手が出産に立ち会うために最長3日間離脱できる仕組みが整っている。
2025年4月、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が実際にこの制度を利用して出産立ち会いを行ったことが国内で話題となり、「日本のプロ野球にも同様の制度が必要ではないか」という声が一気に高まった。この国際的な潮流が、NPB改革の大きな後押しとなった。
「父親リスト(Paternity List)」はメジャーリーグは2011年に導入された制度です。出産予定の48時間前からリスト入りすることができ、最短で1日、最長で3日間(連続)取得することができます。大谷翔平選手は2025年4月18日~19日の2日間利用しました。
補足
日本人選手は、大谷翔平選手も含め、青木宣親選手(13年・ブルワーズ)、川﨑宗則選手(13年・ブルージェイズ)、前田健太投手(18年・ドジャース)、田中将大投手(19年・ヤンキ-ス)、ダルビッシュ有投手(22年・パドレス)、鈴木誠也選手(22年・カブス)の7人が、この制度を利用しています。
② 選手会からの継続的な要望
選手会は以前から、家庭やプライベートを尊重する制度整備を求めてきた。
選手会事務局長の森忠仁氏は報道で、
「野球界だけじゃなく、一般社会ではすでに普通に取り入れられている制度。やっと導入できる段階に来た」
とコメントしている(出典:スポニチ2025年10月15日)。
これは、プロ野球が“社会の常識”に追いつく改革であるという象徴的な発言だ。
③ 球団・現場からの実務的要請
これまで短期間だけ家庭事情で離脱したい場合でも、「10日間の登録制限」が壁となっていた。
チーム事情に合わせて柔軟に運用できる仕組みを求める声が現場でも強まり、制度改正の必要性が共有されるようになった。
制度導入によるメリット
- 選手の精神的安定
家族の重要な場面に立ち会えることで、選手が安心してプレーに集中できるようになる。 - チーム運営の柔軟化
短期離脱にも即対応でき、戦力維持と家庭支援を両立できる。 - 社会的評価の向上
「家庭を大切にする球界」というイメージが定着すれば、ファン層拡大や若手育成にも好影響が期待される。
想定される課題と今後の焦点
- 悪用防止策:
短期入れ替えを戦術的に利用されないよう、明確な基準と証明書提出が求められるだろう。 - 球団間の運用格差
制度が球団ごとにバラつかないよう、NPB全体で統一した運用ルールを設けることが課題となる。
今後の展望
2026年シーズンから正式に導入される見通しで、年内にも詳細な規定が公表される予定だ。
初年度は試行的な運用になると見られ、制度の安定化や改善点の抽出が次のシーズンへの鍵を握る。
NPBが今回の決断で示したのは、「選手はただの戦力ではなく、一人の人間である」という理念だ。
働き方の多様化が進む現代社会において、プロスポーツも例外ではない。
慶弔休暇特例の導入は、球界が時代とともに変化しようとしている象徴的な一歩といえるだろう。

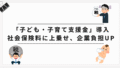

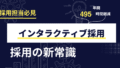
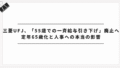

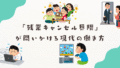
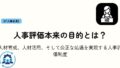
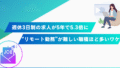
コメント