日本の大手企業で「早期退職勧奨」の動きが報じられています。
従来のコスト削減型リストラとは異なり、「構造改革と成長投資の加速」を掲げた今回の施策。
本記事では、現役人事の視点からニュースを解説し、企業と従業員にとっての示唆を整理します。
報道の概要
化学大手の三菱ケミカルグループは29日、傘下の三菱ケミカルを対象に、50歳以上で勤続3年以上の管理職や一般社員ら約4600人から希望退職を募ると発表した。業績が好調な中で人員削減を行う「黒字リストラ」を実施。事業の構造改革の一環。固定費の削減や要員構成の適正化を図る。募集人数は定めていない。製造に携わる社員は原則として対象外とする。募集期間は11月17~28日で、退職日は来年2月末。退職一時金と特別加算金を支給し、2026年3月期決算で約300億円の損失を計上する見通しだ。三菱ケミカルとして希望退職を募集するのは2020年以来となる。
これらの記事では、大手企業が「人数を定めずに早期退職を募る」という従来にない手法をとり、背景に「構造改革と成長投資の加速」を掲げていることが紹介されています。
現役人事が見る「今回の早期退職勧奨」の特徴
1. コスト削減から「構造改革+成長投資」への転換
従来の「人件費圧縮」とは異なり、企業は将来の成長領域へリソースをシフトすることを目的としています。
人事としては、単なる人員削減ではなく 再配置・人材育成・マインドセット改革 が伴わなければ「痛みだけで終わる」リスクがあると考えます。
2. 「人数を決めない」募集方式の不透明さ
人数を定めない場合、
- 予想以上の応募によるコスト増大
- 想定外のキーパーソン流出
- 社内モラル低下
といったリスクがあります。人事部門には複数シナリオを想定した リスクマネジメント設計 が求められます。
3. 「いつ切られてもおかしくない」時代にどう備えるか
従業員側の視点としては、
- 自己研鑽とスキルアップ
- 変化に適応する柔軟性
- 社内外ネットワーク構築
これらが「安心材料」になります。人事部としても、社員に「自分のキャリアを主体的に描く」重要性を伝える必要があるでしょう。
想定される課題と対応策
| 課題 | 対応策(人事視点) |
|---|---|
| 残留社員のモラル低下 | 勧奨理由の透明化、相談窓口設置、残留意義の明示 |
| 応募過多による予算超過 | 複数シナリオ設計、上限枠の設定 |
| 必要人材の流出 | キーパーソン除外、再配置プランの同時設計 |
| 外部批判 | IR戦略、社会的説明責任の徹底 |
人事からのメッセージ
今回の動きは、年功序列や終身雇用の見直しフェーズに入った象徴的な事例です。
企業は「未来のための変革」として設計し、社員は「選ばれ続ける人材」になるための努力を怠らないことが求められます。
常に学び続け、変化を受け入れ、挑戦する姿勢こそが、これからの時代の最大の安心です。
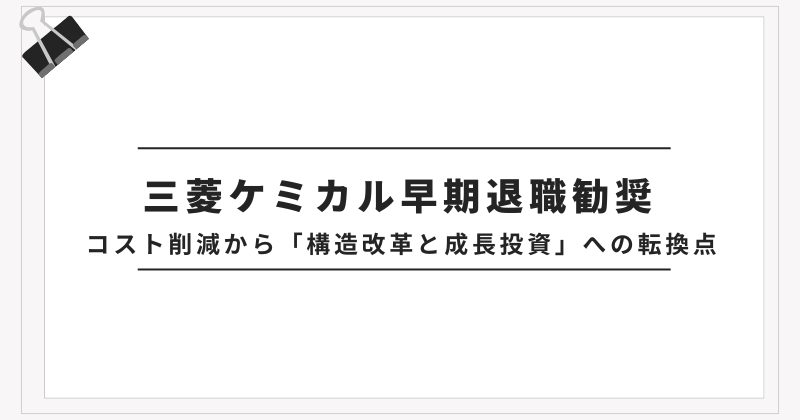


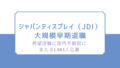
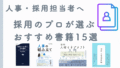
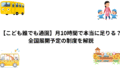
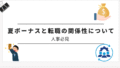
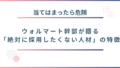
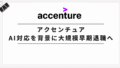
コメント