ニュース記事
「東京の家賃高騰に悲鳴!」住宅手当を増額しても従業員はなお不満 ベテランと若年層のバランスにも苦慮
引用:東洋経済オンライン
東京23区の家賃が上昇し、従業員が職場近くに住むことが難しくなっています。都内にオフィスを構える企業にとっても、家賃補助・住宅手当などの負担が増えていく可能性が高まっています。住宅コストの上昇に対する企業の対応について見ていきましょう。
住宅手当・家賃補助の増額で対応
今回、都内にオフィスがある大手企業68社の人事部門にアンケート調査をしました。
「過去2年間で家賃上昇について対応をしましたか?」と尋ねたところ、次のような回答でした。
「対応していない」の18社と「未定・その他」の7社に関しても、「対応する必要はない」という意見は皆無で、「どう対応するべきか、決めかねている」という声が多く寄せられました。
「都内の借り上げ社宅に住む従業員からは、家賃高騰に悲鳴が上がっています。ただ、東京以外ではまだそれほど家賃が上がっていませんし、持ち家の従業員とのバランスを考慮する必要もあり、決めきれていません」(電機)
「独身寮・社宅など福利厚生を重視する就活生や若手従業員が増えており、独身寮・社宅を充実させる必要があると人事部門では考えています。ただ、経営陣のこの問題への理解は低く、対応できていません」(小売り)
「対応した・対応を決定済み」という43社は、以下のような対応を実施していました(複数回答)。
- 借り上げ社宅の家賃補助の増額 (27社)
- 住宅手当の増額 (13社)
- リモートワークの拡大 (6社)
- 新幹線通勤の適用範囲の拡大 (4社)
- 企業所有社宅・独身寮の導入 (2社)
このうち、回答数が多かった①借り上げ社宅の家賃補助の増額②住宅手当の増額について、印象的なコメントを紹介します。
「昨年、借り上げ社宅の家賃補助の金額を3割引き上げました。かなり思い切って引き上げたつもりですが、従業員からは『これっぽちの引き上げでは不十分』と言われ、経営陣からは『金を使わずに従業員の不満を抑えるのが人事部の仕事だろ』と叱責され、散々でした」(物流)
「住宅手当を平均月6000円増額しました。本当は東京都内の借り上げ社宅への家賃補助だけで済ませたかったのですが、『大阪でも家賃が高騰している』『借り上げ社宅だけでなく、マイホームでも住宅関連費用が上がっている』と話が大きくなり、結局、対象を限定せず住宅手当を引き上げることになりました」(機械)
対応はしたが、問題が解決したわけではない
「対応した・対応を決定済み」と回答した人事部門担当者にヒアリング調査をしたところ、「この問題が解決したとはまったく思っていない」(素材・商社など)「今回の対応はあくまでも応急措置」(輸送機・建設など)という意見が多数ありました。
「首都圏では今後も家賃高騰が見込まれる」(エネルギー)というのもありますが、社宅など福利厚生や働き方について、次の点で人事部門の考えが大きく揺れ動いているようでした。
バブル崩壊後、多くの日本企業が「持たざる経営」、つまり資産をできるだけ持たないという方針を打ち出しました。それを受けて人事部門は、社宅・独身寮を売却し、従業員の持ち家取得を奨励・支援してきました。⑤企業所有社宅・独身寮の導入は、この方針に反します。
「社宅・独身寮を復活してほしいという従業員の声がたくさん届いています。しかし、『持たざる経営』『持ち家取得推進』という長年続いた方針を転換するべきなのか、経営陣の間でも人事部門内でも、議論が割れています」(輸送機)
また、コロナ禍を受けて多くの日本企業がリモートワークを推進しました。しかし、2023年頃から原則出社に方針転換する企業が続出しました。③リモートワークの拡大は、現在の原則出社という方針に反します。
「コロコロ方針を変えてリモートワークを推進することに人事部門は反対です。ただ、従業員からの復活要望は根強いですし、経営陣からは『ゼロベースで働き方のあるべき姿を考えよ』という指示が来ています。今後は、家賃補助の増額でお茶を濁すことは許されません」(サービス)
転勤廃止の流れで社宅・独身寮は不要に
さらに、企業が社宅や独身寮を用意する大きな理由として、人事異動で従業員が全国各地に転勤するという仕組みがあります。近年NTTなど一部の大手企業が転勤廃止の方針を打ち出しており、実現すれば社宅・独身寮の必要性が低下します。
「共働きの社員が増えていることを受けて、転居を伴う転勤を廃止することを検討しています。ただ、実際にやるとなると、社宅・独身寮といった福利厚生だけでなく、採用・人事評価・教育など色々な人事関連制度に影響が及ぶことから、まだ決まっていません」(物流)
このように、多くの人事部門担当者は、足元の家賃高騰には①借り上げ社宅の家賃補助の増額や②住宅手当の増額で対応しつつ、より抜本的な人事制度改革でこの問題を解決しようと模索しているようです。
ところで、一連のヒアリングで最も印象に残ったのは、「家賃高騰への対応は、本質的には若年層対策です。いま人事担当者は若年層対策で疲弊しきっており、状況がさらに悪化しそうです」(専門商社)というコメントです。どういうことでしょうか。
独身寮に住むのは、若年層の従業員です。社宅に住むのは、まだ自宅を購入していない比較的若い層です。近年、就活生が会社選びで独身寮・社宅の有無を重視するようになっています。つまり、家賃高騰対策は、主に若年層のためのものです。
近年、人事部門では、若年層対策の業務が激増しています。新卒採用活動は、以前は季節労働でしたが、通年化しています。インターンが長期化し、会社説明会などイベントの開催数も増えました。内定者のフォローも、昔はあまりなかった業務です。
しかも最近では、苦労して採用した新人が、短期間であっさり辞めてしまいます。新人を辞めさせないように、人事部門担当者は、新人フォローアップ研修を企画・実施し、バディ制度(新入社員に先輩社員が付いて面倒を見る制度)を設計・運営しなければいけません。
人事部門はすでに大忙し
新人・若手が辞めたら第二新卒など若手を中途採用しなければいけません。採用担当者は、一年中、採用面接をしています。その前に、エージェントとの付き合いも欠かせません。
このように人事部門担当者は、すでに若年層対策の業務に忙殺されており、そこに新たに家賃高騰対策の業務が加わるわけです。人事部門担当者がさらに疲弊する姿が目に浮かびます。
はたして、この人事部門担当者の苦境は、今後も続くのでしょうか。
カギを握るのは、ジョブ型雇用と生成AIの普及です。ジョブ型雇用は、ジョブ(職務)に空きが出たら採用する欠員採用が基本で、入社してすぐに活躍できる即戦力が求められます。生成AIが普及すれば、今は若年層が担っている単純業務が生成AIに置き換わります。つまり、ジョブ型雇用と生成AIの普及によって、若年層の重要性は劇的に低下するでしょう。
アメリカではすでにこうした状況になっています。アメリカではジョブ型雇用のため、もともと若年層の失業率が高めですが、最近IT大手が新人の採用を絞ったことから、「就職氷河期」が訪れています。従来は新人が担っていたプログラミングコードの作成などを生成AIに置き換えたためです。
ひるがえって日本では、ジョブ型雇用も生成AIも、まだ普及が始まったばかり。当面は新人・若年層が必要で、人事部門担当者は家賃対策に向き合わなければならない日が続くでしょう。
人事として読んで感じたこと(率直な感想)
「金を使わずに不満を抑えるのが人事の仕事だろ」→その言葉を聞いたら担当は辞めたくなる
経営層からそうした期待が出ると、現場の人事担当は板挟みになります。制度案を作っても「予算ゼロでやってくれ」と言われれば、実効性のある施策は打てませんよね。
結果、担当の疲弊が進み、優秀な人事が流出するリスクがあると強く感じます。
人事を流出させ、販管費を削減する考えが経営層にあるならこのアクションは正しくなると感じます。
住宅手当増額は「ネガティブ離職」を防ぐための有効策
更新で家賃が大幅に上がり、手取りが圧迫される層は実際に存在します。
生活苦→退職(通勤先変更や転職)を避けるため、一定の増額は合理的です。
短期的な人材流出を止めるには費用対効果が良い場面が多いでしょう。
ただし従業員は「手当だけで解決しない」ことを薄々理解している
現場の目線では「住宅手当は増えるが限界がある/恒久的にカバーされるとは限らない」と認識している人が多い。
だからこそ副業やスキル形成で収入源を増やす個人の動きも出ている、というのが私の観察です(人事としては副業解禁や副業支援、学習支援を制度化する余地あり)。
採用で都心回避の志向が出てきている
物価高・家賃高に加え、「満員電車を避けたい」という生活の質を重視する志向から、就活生や転職者が都心勤務よりも埼玉・千葉・神奈川など近郊勤務を希望する傾向が出ています。採用計画や勤務地設計に影響が出始めています。
現場の人事が今すぐ取り組める実務的アクション
- 影響把握のための“賃料ショックマップ”作成
社員の居住エリア・家賃・更新月をまとめ、どの部署・年代にショックが集中するか可視化する(優先度高)。 - 一時的増額+条件付き支援の導入
更新時の一時補助(月額●●円を最大◯回まで等)や、子育て・介護など生活負担が高い層への優先支援を設計する。 - 副業・スキル支援の制度化
副業ガイドライン、社内副業マッチング、学習補助(資格・講座費用の補助)で個人の収入源と市場価値を高める支援を行う。※中長期的離職抑止につながる。 - 採用ポジショニングの見直し
都心勤務の魅力を再構築する(リモート/ハイブリッドの明確化、福利厚生での差別化、通勤補助の充実など)。地方通勤希望者向けに面接場所や説明会の地方展開も検討。 - 経営層向けの「コストvs離職リスク」ダッシュボード作成
住宅手当拡充が短期的な人材流出をどれだけ抑えるかの試算を提示し、理解を得る。人事は“感情”ではなく“数値”で説得するべきです。 - 借上社宅やサテライトオフィスの設置場所検討
借上げ社宅やサテライトオフィスを23区内特に本社が近い場所に設置することは費用が高くなり経営を圧迫しかねないため、社員が多く住んでいる場所付近にサテライトオフィスを立て、勤務可能にするや借上社宅も社員が多く住んでいる場所付近にすれば、会社と社員側で負担する家賃の金額が抑えられます。また家賃補助を上げることが厳しい場合は事業の地方展開をして首都圏勤務希望以外の求職者を取り込みに行くのがベターです。
注意点(落とし穴)
- 一律の増額は持ち家社員や地方在住者との不公平感を生む。公平性と説明責任が必要。
- 経営側の短期コスト志向と人事の長期的視点のズレは、早めに対話で埋める必要あり。
最後に
短期的には住宅手当の増額は「有効な火消し」になりますが、それで安心してはいけません。
人事は「生活の安全網」と「個人の自走力(副業・スキル)」の両輪で施策を設計するべきです。経営には、人材流出のコストを見える化して投資判断を促しましょう。
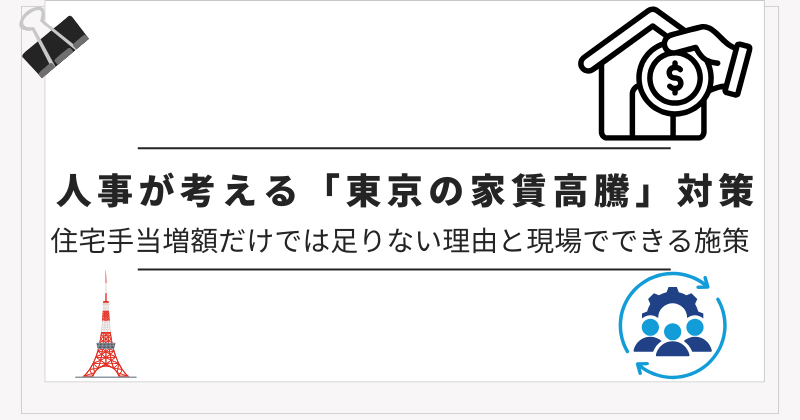
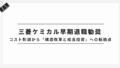

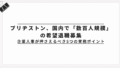
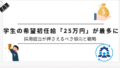
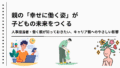

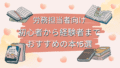

コメント