人事担当者の皆さん、特にIT業界の人事として日々奮闘されている皆さん、こんにちは!
IT業界は、技術の進化が目覚ましく、常に新しいトレンドが生まれるダイナミックな世界です。この業界で働く皆さんの「給与」は、一体どのように決まっているのでしょうか?「IT業界は給料がいい」というイメージがある一方で、職種やスキル、企業の特性によって大きな差があるのも事実です。
「IT業界の他社の賃金ってどうなっているんだろう?」
「自社の給与水準は、業界内で見て適正なのだろうか?」
こうした疑問や課題を抱えているIT人事の方も多いのではないでしょうか。
今回は、IT人事の皆さんが自社の賃金戦略を立てる上で役立つよう、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の公開データを参考に、IT業界の賃金推移に特化して深掘りしていきます。データやトレンドを交えながら、あなたの会社の給与が「なぜ」そのようになっているのか、そして今後どうあるべきかを探っていきましょう。
IT業界の賃金は「成果」と「専門性」がカギ
IT業界の賃金構造を語る上で、最も重要なキーワードは「成果主義」と「専門性」です。
一般的な製造業などの産業で長く見られた年功序列とは異なり、IT業界では個人の年齢や勤続年数よりも、以下の要素が賃金に強く反映される傾向にあります。
- スキルと専門性: 特定のプログラミング言語、クラウド技術、AI/データサイエンス、セキュリティといった高度な専門スキルを持つ人材は、市場価値が高く、それに見合った高水準の賃金を得やすいです。常に最新技術を学び続ける学習意欲も評価対象となります。
- 成果と貢献度: プロジェクトの成功への貢献、新サービスの開発、システムの効率化など、具体的な成果やビジネスへのインパクトが賃金に直結します。個人のパフォーマンスが明確に評価され、それが報酬に反映される成果主義が浸透しています。
- 希少性: 市場に供給が少ない特定の専門スキルや経験(例:特定のSaaS導入経験、ニッチなクラウド技術など)を持つ人材は、獲得競争が激しいため、より高い賃金が提示される傾向にあります。
- 事業モデルと収益性: SaaS(Software as a Service)のような高収益型ビジネスモデルを展開する企業や、独自の技術で高い市場シェアを持つ企業は、従業員へ還元できる原資が大きいため、賃金水準も高くなる傾向にあります。
データで見るIT産業の賃金水準と推移、そして「若さ」
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」は、日本の賃金の実態を把握するための重要な統計データです。ここでは、その中でも「情報通信業」のデータを中心に見ていきましょう。
賃金構造基本統計調査における「情報通信業」には、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、通信業などが含まれます。IT業界全体を包括するものではなく、ゲーム産業やWebサービス専業のスタートアップなど、一部の業態は含まれない場合もあります。また、非正規雇用者も含まれた平均値であることに留意してください。
1. IT産業の平均賃金は全体と比較して高い傾向
令和6年のデータ(男性・女性計、所定内給与額)によると、情報通信業の平均賃金は約374.9千円(引用元:賃金構造基本統計調査 令和6年より)となっており、全産業平均(約326.3千円)と比較して高い水準にあることが分かります。
これは、前述したIT業界の「専門性」や「成果」が賃金に反映されやすい特性を裏付けるものと言えるでしょう。
特に、電気・ガス・熱供給・水道業(約437.5千円)や金融業,保険業(約410.6千円)に次ぐ水準であり、日本の産業の中でも比較的高待遇な位置づけにあることがデータからも読み取れます。
2. IT産業は「平均年齢が若い」という特徴
賃金構造基本統計調査のデータでは、各産業の平均年齢も公表されています。情報通信業の平均年齢は、全産業平均(約43歳)と比較して約37歳と、明らかに若い傾向にあります。
これは、IT産業が比較的新しい産業であること、技術革新が速く新しい知識や柔軟性が求められること、そして若手層の参入が多いことなどが複合的に影響しています。
この「若さ」がIT産業の賃金構造に与える影響は以下の通りです。
- 高水準の初任給・若年層給与: 若手人材の需要が高いため、入社時の給与や20代・30代前半の賃金が他産業に比べて高い傾向にあります。
- 年齢階級別の賃金推移の特殊性: 前述の通り、年齢とともに賃金が上昇するものの、40代後半以降の伸びが他の伝統的な産業ほど顕著ではない、あるいはピークアウトが早い可能性があるのは、年齢よりもスキルや最新技術への対応力が重視されるIT業界の特性を強く反映しています。若いうちから高水準の給与を得られる反面、スキルアップを怠ると賃金が頭打ちになるリスクもはらんでいます。
他業界と比べて平均年齢が若いということは、若者が多く業界に入ってきてくれているまたはベテランが他業界に流れてしまっている可能性がありますね!
平均年齢が若い中でも平均賃金が3位であることは、今後成長が期待される業界であることの証拠とも言えますね。
3. 年齢階級別の賃金推移:緩やかな上昇とピークアウトの傾向
IT産業における年齢階級別の賃金データを見ると、一般的に以下のような傾向が見られます。
| 年齢階級 | 情報通信業の賃金傾向(男女計・所定内給与額) | 全産業平均との比較 |
| ~24歳 | 他の産業と比較しても比較的高い水準からスタート。 | 全産業平均より高め。 |
| 25~34歳 | 経験とスキルの積み重ねにより、賃金が大きく上昇する時期。 | 全産業平均より高め。 |
| 35~44歳 | マネジメント層や高度専門職として賃金がピークに達する傾向。 | 全産業平均より高め。 |
| 45~59歳 | 賃金の伸びは緩やかになるか、一部でピークアウトが見られることも。 | 全産業平均より高めだが、伸び率は鈍化傾向。 |
| 60歳~ | 再雇用等により賃金水準は下がる傾向にある。 | 全産業平均と同様の傾向。 |
このデータからも、IT産業では若年層から比較的高水準の給与を得られる一方で、40代後半以降の伸びが他の伝統的な産業ほど顕著ではない、あるいはピークアウトが早い可能性があることが示唆されます。これは、「年齢」よりも「スキル」や「最新技術への対応力」が重視されるIT業界の特性を反映していると言えるでしょう。
特にSIerなどの業界では一人当たりの単金が年齢を重ねただけでは、なかなか上がりずらいため45~59歳からの賃金の伸びが緩やかになる傾向があります。私もSIer業界に属していて賃金カーブを考える事もしていますが、他業界に桑部たらピークアウトを比較的早く設定していますし、役職定年も早めに設定しています。
そんな中でキャリアの途中で新しい技術を習得したり、マネジメント職に転向したりすることが、賃金の上昇に直結しやすい構造です。
4. 企業規模別の賃金格差:大企業が優位だが、スタートアップも高待遇の可能性
賃金構造基本統計調査では、企業規模別の賃金も確認できます。一般的に、IT産業においても企業規模が大きいほど平均賃金が高い傾向にあります。これは、大企業ほど安定した収益基盤を持ち、福利厚生なども充実しているためです。
しかし、IT業界特有の事情として、急速に成長しているスタートアップやベンチャー企業の中には、資金調達力や、市場をリードする独自の技術を持つことで、大企業に匹敵する、あるいはそれを超える高待遇を提示するケースも少なくありません。
特に、ストックオプション制度などを導入し、企業成長と個人の報酬を連動させることで、優秀な人材を引き付けています。
このため、IT業界の賃金を分析する際には、単に企業規模だけでなく、事業の成長ステージやビジネスモデルも考慮に入れる必要があります。
IT人事として賃金構造を最適化するための戦略
IT業界の賃金トレンドを踏まえ、自社の賃金構造を最適化し、優秀な人材を獲得・定着させるためにIT人事として考慮すべきポイントは以下の通りです。
- 市場価値に基づいた賃金ベンチマークの徹底: 定期的にIT業界に特化した賃金サーベイ(外部機関のレポートやコンサルティング会社による調査など)を活用し、自社の給与水準が市場と比べてどの位置にあるかを細かく把握しましょう。特に、採用競争が激しいエンジニア職やデータサイエンティストなどの職種・スキルにおいては、市場価値を意識した報酬設計が不可欠です。
- スキル・成果主義への継続的なシフト: IT業界の特性に合わせ、年齢や勤続年数よりも、個人のスキル習得やプロジェクトでの貢献度、事業へのインパクトが賃金に直接反映される仕組みをさらに強化しましょう。
- スキルマップの整備: 職種ごとに必要なスキルを定義し、各スキルの習熟度に応じた評価基準を明確にする。
- 客観的な成果評価指標の導入: OKR(Objectives and Key Results)やMBO(Management by Objectives)などを活用し、個人の目標達成度やチームへの貢献度を具体的に評価する。
- ジョブ型雇用の推進: 職務内容(ジョブディスクリプション)と求められるスキル・責任範囲を明確にし、それに応じた報酬レンジを設定する。
- 明確なキャリアパスと報酬連動の提示: 社員が「このスキルを習得すれば、これくらいの報酬レンジになる」「この職務を遂行できるようになれば、この役職に昇進し、給与も上がる」といった、具体的なキャリアパスとそれに連動する報酬体系を明確に示しましょう。これにより、社員の自律的な学習意欲とエンゲージメントを高め、長期的なキャリア形成を支援できます。
- 非金銭的報酬の最大化と戦略的アピール: 高騰するIT人材の賃金競争において、金銭的報酬だけで差別化するのは限界があります。給与以外の非金銭的報酬(福利厚生、働きがい、ワークライフバランスなど)を充実させ、それを積極的にアピールすることが重要です。
- 柔軟な働き方: フルリモート、ハイブリッドワーク、フレックスタイム制など。
- 自己成長機会: 最新技術の研修支援、資格取得支援、社内外勉強会の実施。
- 裁量権と責任: 若手にも大きな仕事を任せる風土、イノベーションを推奨する文化。
- 企業文化: オープンでフラットな組織、チーム間の協力体制、ミッションへの共感。
- 福利厚生: 健康経営への注力、リフレッシュ休暇、ユニークな手当など。
- 賃金決定プロセスの透明性向上: 賃金決定のプロセスや評価基準について、社員への透明性を高めることで、報酬に対する納得感と信頼感を醸成します。定期的な1on1ミーティングでのフィードバックや、評価結果の丁寧な説明を通じて、社員が自身の報酬を納得できる環境を作りましょう。
まとめ:IT業界の特性と「若さ」を理解し、競争力ある賃金戦略を
IT業界の賃金構造は、技術革新のスピード、人材の流動性、そして成果への強い志向によって、他の産業とは異なる独自の進化を遂げています。
厚生労働省の統計データからも、IT産業が比較的高水準な賃金であること、平均年齢が若いこと、そして年齢よりもスキルや専門性が重視される傾向が見て取れます。
IT人事の皆さんは、これらの業界特性を深く理解し、常に最新の市場動向を捉えることが求められます。単に「給与が高いか低いか」だけでなく、「なぜその賃金が支払われるのか」という背景を深く掘り下げ、スキルと成果を正当に評価する競争力のある賃金戦略を構築していきましょう。
このブログ記事が、IT業界の賃金分析と、それを基にした皆さんの人事戦略立案の一助となれば幸いです。

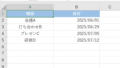
コメント