2011年にMLB(メジャーリーグベースボール)と選手会の合意で導入された父親リスト(Paternity List)は、選手が配偶者の出産に立ち会うために最長3日間、チームを一時離脱できる制度です。
ロースターから一時的に外すことで代替の選手を起用でき、選手は給与や登録上の大きな不利益を被ることなく家族と過ごすことができます。制度自体は2011年に始まり、その後利用者は増加しました。
なぜ必要だったのか?導入の背景と意義
かつては出産に立ち会うためのチーム離脱が「制限リスト」や別扱いとなり、無給扱いやファン・メディアの非難を受けることもありました。
家族の一大イベントに立ち会う権利を制度的に保障することで、選手のワークライフバランスを尊重すると同時にチーム運営側も代替手段(短期的なロースター差替え)を取りやすくした点が評価されています。
導入以降、制度を使う選手は年々増え、現代のMLBでは“3日間の父親休暇”はごく一般的な選択肢になりました。

利用事例:世界的スターから日本人選手まで(実例多数)
MLBの父親リストは多くの選手に利用されています。近年の代表例を挙げると――
上記は日本人選手でもすでに複数の実例があることを示しています。MLBは選手国籍に関わらず同じルールが適用されるため、文化的・言語的な背景にかかわらず制度を利用しやすい環境が整っています。
利用が増えた理由――データで見る変化
導入直後の2011年は利用者が少なかったものの、その後は着実に増加し、近年は毎年数十名が父親リストを使うようになっています。
ファングラフなどの解析では2011年以降、年々増え、ここ数年は年間で40〜50人前後が利用していると報告されています。
選手・球団双方の認識変化や、メディア/ファンの受け入れが進んだ点が背景です。
日本のプロ野球(NPB)との比較:差はあるか?
NPBではMLBのように“統一された父親リスト”という制度名や明文化は一般的ではなく、球団ごとの特別休暇や勤務規則の範囲で個別対応されるケースが多いです。
近年は働き方改革や育児支援の流れから、選手の家族イベントに配慮する球団も増えていますが、MLBのようにルールで明確化されているかどうかは球団や選手会との合意内容に依存します。
MLBの事例はNPBの制度設計にヒントを与える部分が大きいと言えるでしょう。
なぜもっと増やしてほしいのか?——ファン・球団に向けた提言
- 人間性の尊重:
出産や育児は一生に一度の瞬間がある。選手がそれに立ち会えることは、家族の絆や精神的安定につながり、長期的には選手のパフォーマンス向上にも寄与します。 - 制度化の透明性:
MLBのようにルール化しておけば、球団ごとの差異や「言いにくさ」が減り、利用ハードルが下がります。 - 周囲の理解促進:
ファンやメディアの受け止め方も変わっています。かつてのように「欠場=怠慢」と見做される時代ではありません。選手が家族を優先する姿はファンの共感も呼びます。
まとめ:家族もチームの一部だ
MLBの父親リストは「選手の人間的な瞬間」を尊重する先進的な制度です。
日本人選手の利用実績も増えており、大谷・ダルビッシュ・鈴木誠也・前田健太・青木宣親らの事例は、同じルールが国籍を問わず機能することを示しています。
今後は球団・リーグ・選手会の理解を深め、制度利用が当たり前になることで、選手とその家族、そしてファンにとってより健全なスポーツ文化が育っていくはずです。

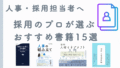

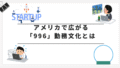




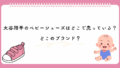
コメント